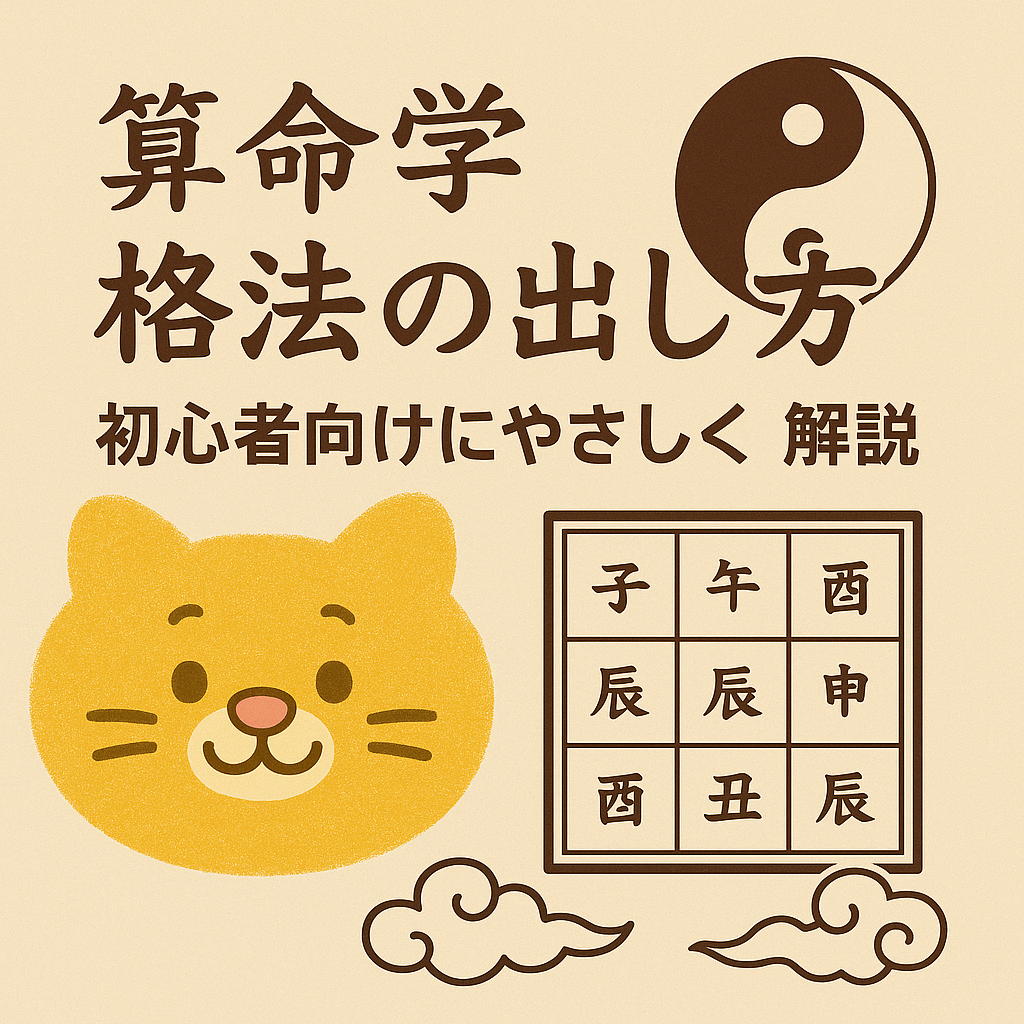算命学を学び始めた方の中には、「格法(かくほう)ってなに?」「どうやって自分の命式から格を出すの?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、格法とは何か、そして具体的にどうやって格を判断していくのかを、初心者の方にもわかりやすく解説します。
陰占・陽占・後天運という三つの観点から格を読み解いていく方法を、ステップごとに丁寧に説明していきますので、安心して読み進めてくださいね。
目次
算命学における格法の出し方がわからない!格法の基礎知識
格法とは何か
算命学における格法(かくほう)とは、陰占・陽占・後天運の三つを組み合わせて、命式の中から特定の構造や意味合いを見出す技術です。
- 陰占:生年月日の干支(かんし)から五行バランスや相生・相剋を読み取ります。
- 陽占:十大主星や十二大従星など、性格や行動傾向を示す配置です。
- 後天運:大運・年運など、時の流れによる運気の影響。
この三つを総合的に見ることで、その人の命式が「格」に入るかどうかを判断するのが格法です。
算命学の入門書やアメブロの人気ブログ「さる山さる子の算命学」などでも、格法は中級以上の理解が必要とされますが、基本さえ押さえれば初心者でも読み解きが可能です。
完全格 vs 一点破格の判別
完全格に「非常に近い」命式でも、一部に異なる要素(たとえば1つだけ異質な五行など)がある場合は「一点破格」となります。
局法との違い
格法とよく混同されるのが局法(きょくほう)です。
- 局法:人体星図の主星のみを用いた読み方。
- 格法:陰占・陽占・後天運すべてを統合的に判断します。
つまり、局法が「ある一面の分析」に留まるのに対し、格法は命式全体を立体的に把握するのが特徴です。
格の分類と代表的なタイプ
従化五格とは
格法の中でも特に有名なのが従化五格(じゅうかごかく)です。
これは、ある一定の条件を満たすと「特殊な命式構造」として高評価される格です。
代表的な五つは以下のとおり:
- 従財格(じゅうざいかく)
- 従生財格(じゅうせいざいかく)
- 従官格(じゅうかんかく)
- 従生格(じゅうせいかく)
- 殺印相生格(さついんそうしょうかく)
これらは命式内の五行や通変星の偏りによって成立します。
たとえば、身弱で財星が多い場合、従財格になることがあります。
その他の雑気格や玄流八格など
従化五格以外にも、多種多様な格が存在します。
- 雑気格(ざっきかく):通変星の混在した命式から派生する格。
- 玄流八格(げんりゅうはっかく):一部の流派で独自に分類された格。
命式の見方や使う理論によっても、格の種類や数は異なります。
「知命立命」や「心地よい風景」などのアメブロでも、設例を用いてわかりやすく紹介されています。
格の出し方ステップ
陰占で日干・干支配列を確認
まずは命式の中心となる日干(にっかん)を確認しましょう。
日干が他の干支とどう関係しているかが、格法において重要です。
- 自分を生じる・助ける:身強(しんきょう)
- 自分を剋する・泄する:身弱(しんじゃく)
干支配列から、日干が浮いているかどうか、何に囲まれているかを分析します。
身強・身弱の判定と貫索星・石門星の有無
格法の多くでは身弱であることが条件となる場合が多いです。
さらに、「貫索星(かんさくせい)」や「石門星(せきもんせい)」が命式にあると、「自我が強い=従化しにくい」と見なされることも。
入格条件の一つとして、
- 貫索・石門がない
- 身弱である
この2点がよくチェックされます。
陽占で十大主星/十二大従星の構成を確認
次に陽占を確認します。十大主星や十二大従星のバランスや偏りが、格との一致に影響します。
- 官星(車騎・牽牛)ばかり:従官格の可能性
- 財星(禄存・司禄)ばかり:従財格の可能性
整体占いやアメブロの命式解説でも、この星の偏りが格の根拠として解説されています。
後天運との兼ね合いを見る
格が成立していても、大運や年運の巡りで格が破れる(破格)ことがあります。
後天運が五行バランスを崩すような場合、格の効力が低下することも。
たとえば、大運で貫索星が巡ると従化が壊れる場合があります。
これが「破格」という状態です。
判定の注意点と活用上の心得
破格(部分的・後天運による崩れ)とは
格に見えても、よくよく見ると条件を満たしていないことがあります。
- 五行の中和がある
- 十大主星で貫索星が出ている
- 後天運で格が壊れる
このような場合は「部分格」や「破格」と判断されます。過信しないようにしましょう。
格に囚われすぎない注意喚起
格法はあくまで命式分析の一側面です。
全体の命式バランスや、人物の実際の行動と合わせて読み解く視点が大切です。
格にこだわりすぎて、「格に合わないから不運だ」と決めつけるのは本末転倒。
あくまで参考材料として活かしましょう。
よくある例とシンプル事例集
入格の代表例
たとえば次のような命式は、典型的な従財格の例として紹介されます:
- 日干が弱く、全体に財星ばかり
- 陽占でも禄存星・司禄星が集中
- 貫索星・石門星がゼロ
このような例では、「他者に従うことで財運が伸びる」という運命傾向が表れやすいとされます。
よく混同される事例とその見分け方
- 準格:条件を一部満たしているが、不完全
- 部分格:一部の干支だけが格に一致
- 破格:運や構造によって格が成立しなくなる
これらを見分けるには、陰占・陽占・後天運の三つをすべて確認することがポイントです。
格法を活かす開運アプローチ
上格・中格・下格別の考え方
格の評価は「上格・中格・下格」としてランク分けされることもあります。
- 上格:強く格が整っており、成功しやすい構造
- 中格:条件付きで活かせる
- 下格:格に至らないが、工夫で補える
それぞれに適した生き方や職業の傾向があります。
格と現実行動のつなぎ方
命式に合った行動をすることで、運気を引き寄せることができます。
例:
- 従財格 → 補佐役・金銭管理などに適性
- 従官格 → 組織の中で役割を果たすことに安定感
また、心のあり方=人徳を高めることが、命式の潜在力を引き出すカギになります。
締めくくり(まとめ)
格法の出し方は以下の流れが基本です:
- 陰占で日干と干支配列を確認
- 身強・身弱や貫索星・石門星の有無を判断
- 陽占で星の偏りを見る
- 後天運との兼ね合いを確認
格は命式を読み解く上での「特別な視点」ですが、格に囚われすぎず、自分の命を活かすためのヒントとして柔軟に活用することが大切です。
★次のアクションとして…
自分の命式を無料の命式算出ツールで出してみましょう。
例えば「さる山さる子の算命学」や「整体占いブログ」などでは初心者にもわかりやすい命式表示があります。
ぜひ自分の命式を見ながら、この記事のステップを一つずつ実践してみてくださいね。